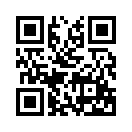2015年06月24日
「沖縄に内なる民主主義はあるか」第五章 普天間飛行場の移設は辺野古しかない全文
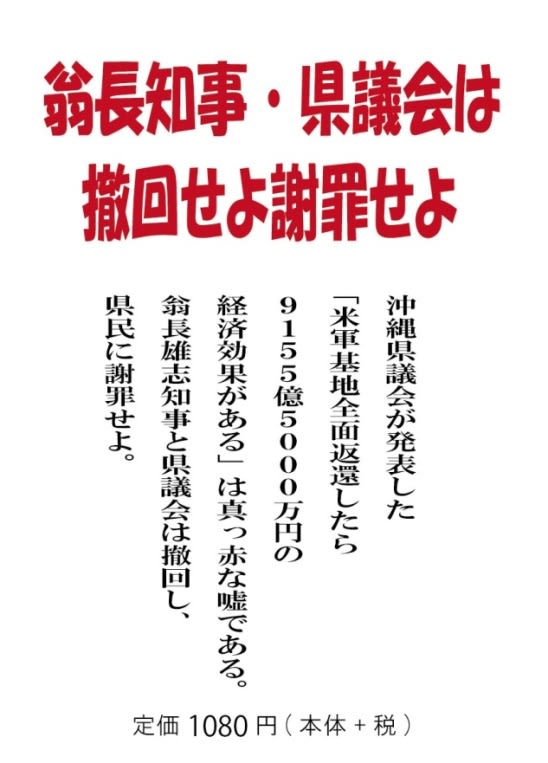

「翁長知事・県議会は撤回せよ謝罪せよ」
「一九七一Mの死」
4月30日より県内書店で発売しました。
本の説明はこちら
県内取次店
沖縄教販
○県外は書店で注文できます。
県外取次店
(株)地方小出版流通センター
「沖縄に内なる民主主義はあるか」
第六章 八重山教科書問題はなにが問題だったか全文
第五章 普天間飛行場の移設は辺野古しかない全文
第四章 基地経済と交付金の沖縄経済に占める深刻さ全文
第三章 県議会事務局の米軍基地全面返還したら9155億5千万円経済効果試算の真っ赤な嘘全文
第二章 命どぅ宝とソテツ地獄全文
第一章 琉球処分は何を処分したか全文
ヒジャイ掲示板へ
ヒジャイ掲示板
クリックお願いします
にほんブログ村
第五章 普天間飛行場の移設は辺野古しかない
沖縄県の人口の推移
大正 9年(1920年) 57万1,572人
大正14年(1925年) 55万7,622人
昭和 5年(1930年) 57万7,509人
昭和10年(1935年) 59万2,494人
昭和15年(1940年) 57万4,579人
昭和25年(1950年) 69万8,827人
昭和30年(1955年) 80万1,065人
昭和35年(1960年) 88万3,122人
昭和40年(1965年) 93万4,176人
昭和45年(1970年) 94万5,111人
昭和50年(1975年) 104万2,572人
昭和55年(1980年) 110万6,559人
昭和60年(1985年) 117万9,097人
平成 2年(1990年) 122万2,398人
平成 7年(1995年) 127万3,440人
平成12年(2000年) 131万8,220人
平成17年(2005年) 136万1,594人
平成22年(2010年) 139万2,503人
戦前の沖縄の人口は60万人が限度だった
人口の推移で注目すべきは、1920年から1940年の人口は50万人台で増えたり減ったりしていて60万人を超えた年がないことである。これは偶然ではない。戦前の沖縄の産業は農業中心であった。農業は一家族が普通に生活するためには一定の広さの畑が必要である。沖縄全体の農地では農業中心の沖縄ならば人口は60万人が限界であると言われていた。人口調査にみられるように戦前の沖縄の人口は60万人近くで増減を繰り返していて、60万人を超えた年がなかった。これは偶然ではなく、60万人を超える人間は沖縄では生きていけないことを示している。
戦後は電気、水道、車、電化製品などが生活の必需品となり、戦前よりもお金のかかる生活になった。もし、戦後の沖縄が農業中心であったなら、沖縄の人口は戦前の人口60万人よりかなり下回るはずである。
農業中心の沖縄の人口を推計する
沖縄県全体の農業収入は約930億円であり、2009年度の県民の平均所得は約204万円である。農家の所得を県民所得と同じ204万円とし、肥料、農器具、運送などの必要経費が70万円と推定すれば農家の年収は274万円である。沖縄が農業中心社会だとすると、
930億円÷274万円=3万3941戸
一戸五人家族とすると、
3万3941戸×5=16万9705人
2009年度の県民の平均所得と同じ所得を農家が得るとしたら農家の人口は16万9705人
である。沖縄全体が農業中心になり、農地が現在の1・5倍になったと仮定すると、農家の人口も1・5倍になるから25万4558人となる。県の人口が農業人口の1・5倍だとすると38万1837人が県の人口と推計できる。
農業中心の沖縄県の人口はどんなに多く想定しても40万人くらいである。戦前の沖縄は電気・ガスや電化製品・車などがなかったから60万人近くの人々が生存することができたが、文化製品に囲まれた戦後の生活なら生活費が高騰しているから戦前より人口はかなり減少してしまう。現在の沖縄の人口は140万人である。農業中心の沖縄なら100万人近くの人間が沖縄から消えなければならない計算になる。
沖縄本島の北部や離島は過疎化が進んでいるが、過疎化が進む原因は北部や離島の産業が農業中心だからである。北部や離島の実態が沖縄が農業中心の社会になった時の姿である。
美しい自然と農業で豊かな生活が築けると考えるのは大間違いである。農業中心の社会は大地主だけが豊かになる社会であり、土地を持たない人間は貧困生活を強いられるか沖縄を出ていかなければならない運命にある。戦前の沖縄がそうであった。
沖縄が農業中心の産業であったら人口は40万人くらいであっただろうという私の推計をあなたは信じないかも知れない。しかし、それが現実であることを示す実例がある。奄美大島の戦後の人口推移である。奄美大島は沖縄と同じように米軍の統治下にあったが、沖縄より19年も前に本土復帰を果たした。奄美大島には米軍基地はない。産業の中心は農業であり、さとうきびつくりが盛んである。米軍基地のない沖縄が奄美大島と似た経済になるのは間違いない。
奄美大島の人口推移をみると。
昭和 25年 21万6110人
平成 22年 7万0400人
米軍基地がある沖縄の人口は、戦前は60万人以内だったものが平成22年には139万に増加した。しかし、米軍基地のなかった奄美大島の人口は21万6110人から7万0400人へなんと三分の一まで人口は減少しているのだ。もし、沖縄に米軍基地がなくて奄美大島のように農業中心の産業であったら奄美大島と同じように沖縄の人口は減少し続け、戦前の人口60万人の三分の一の20万人になっていた可能性が高い。私の予想の40万人の半分の人口である。
もし、沖縄が戦前と同じ農業中心の産業であったなら、沖縄の人口は20万人からどんなに多くても40万人であったことはまぎれもない事実である。実に100万人から120万人の人間が沖縄から消えることになる。沖縄農業の経済的実力は非常に小さいことを私たちは認識しなくてはならない。特にさとうきびの経済的実力は小さい。さとうきびは1トン2万1000円前後であるが、その内の1万5000円が政府補助金である。さとうきび代金の4分の3は補助金なのだ。
もし、政府の補助金がなければさとうきび産業は壊滅する。さとうきびから経済力の高い農作物への転換はどうしても克服しなければならない沖縄農業の重要な課題である。
沖縄の人口増加は基地経済が原因
沖縄と奄美大島の大きな違いは米軍基地があるかないかである。米軍基地のある沖縄は人口が増え続け、米軍基地のない奄美大島は人口が減り続けた。米軍基地経済が沖縄の経済発展と人口増加に貢献してきたのは明らかである。私たちはこの事実を冷静に受け止めなければならない。
1945年の沖縄戦で10万人近くの県民が戦争の犠牲になったにもかかわらず、1950年の人口は沖縄戦前の1940年より10万人以上も増えて、69万8,827人になっている。敗戦により南方や大陸に移民していた人たちが沖縄に戻されたのとベビーブームの影響だろう。
注目すべきことは、戦前は60万人が人口の限度であるといわれていたのに、戦争が終わって5年後の1950年には沖縄の人口が60万人をかなり超えて70万人近くになっていることである。戦前の農業中心の沖縄では起こるはずのないことである。それも沖縄戦で焦土化した沖縄の農業はまだ回復していなかったはずだから60万人が住むのさえ困難であった。それなのに沖縄の人口は70万人近くになったのである。激戦で焦土化した沖縄で70万人の人々が生活できたのは奇跡である。奇跡が起こったのは戦後の沖縄が農業中心の経済から基地経済へと移ったからである。米軍基地がもたらした経済が沖縄の人口を70万人に引きあげたのである。戦後、沖縄の人口は増え続け、平成23年には140万人を突破した。戦前の農業中心の人口に比べて2倍以上の人口である。
宜野湾市の戦後の経済発展の要因
宜野湾市の人口推移
大正 9年(1920年) 1万2,704人
大正14年(1925年) 1万2,569人
昭和 5年(1930年) 1万2,857人
昭和10年(1935年) 1万3,346人
昭和15年(1940年) 1万2,825人
昭和25年(1950年) 1万5,930人
昭和30年(1955年) 2万4,328人
昭和35年(1960年) 2万9,501人
昭和40年(1965年) 3万4,573人
昭和45年(1970年) 3万9,390人
昭和50年(1975年) 5万3,835人
昭和55年(1980年) 6万2,549人
昭和60年(1985年) 6万9,206人
平成 2年(1990年) 7万5,905人
平成 7年 (1995年) 8万2,862人
平成12年(2000年) 8万6,744人
平成17年(2005年) 8万9,769人
平成24年(2012年) 9万3、189人
1920年から1940年までの人口は1万2,000人代で推移していてほとんど変化していない。戦前の沖縄は農業中心であり、宜野湾も農業中心の村であった。農業を営むには広い農地が必要である。人口に変化が見られないのは農業を営むのに1万3,000人前後が限界であったからだろう。これ以上人口が増えると生活できない者が増える。農地を持たない次男、三男は宜野湾から出て行かなければならなかった。宜野湾が農業中心であったなら、戦後も人口は増えなかったはずである。
終戦直後の宜野湾市の人口は1万5,930人となり戦前よりわずかに増え、その後はどんどん増えていった。人口が増えた原因は農業から基地経済に転換していったからである。軍雇用員、軍用地料、米兵と米兵の家族相手の商売によって宜野湾市の経済はどんどん発展していった。
米軍基地のある宜野湾市の人口増加は6万3688人
昭和35年(1960年) 2万9,501人
平成24年(2012年) 9万3、189人
米軍基地のない糸満市の人口増加は2万5630人
昭和35年 (1960年) 3万3,580人
平成24年 (2012年) 5万9、210人
米軍基地のない石垣市の人口増加は1万0314人
昭和35年(1960年) 3万8481人
平成24年 (2012年) 4万8795人
宜野湾市の人口増加は6万3688人、糸満市の人口増加は2万5630人、石垣市の人口増加は1万0314人である。糸満市も石垣市も経済発展の環境は好条件であり目覚ましく経済は発展しているほうである。しかし、米軍事基地のある宜野湾市に比べると経済発展に大差がある。
普天間飛行場が占める土地のうち、およそ92%は私有地である。このため、賃借料が地主に支払われており、2000年代は軍用地料が60億円台で推移している。宜野湾市には普天間飛行場だけでなくキャンプズケランもある。基地経済が宜野湾市の経済をうるおしているのは間違いない。
普天間飛行場など全ての軍用地が返還されれば、宜野湾市への経済的影響は大きい。
沖縄に米軍基地が存在している理由
沖縄の米軍事基地は沖縄の経済を発展させるために存在しているわけではない。基地経済は付随的なものであり、アメリカが沖縄の米軍基地を必要がないと判断すれば、沖縄の経済とは関係なくアメリカはさっさと米軍基地を撤去するだろう。
アメリカが沖縄に基地をつくったのは旧ソ連、中国等の社会主義圏に対する抑止力のためである。戦後の社会主義国家はすごい勢いで勢力を拡大していった。アメリカは社会主義をもっとも嫌い、もっとも恐れた。アメリカは社会主義の拡大を抑止するために韓国、南ベトナム、台湾、フィリピンなどの国家をバックアップすると同時に、日本本土や沖縄の軍事基地を増強した。本土は自衛隊の軍事力が強化されるに応じて米軍基地を減らしていった。
沖縄の米軍基地強化と密接な関係がある旧ソ連圏の脅威的な拡大
レーニンの死後、独裁的権力を握ったスターリンは、ポーランドやルーマニアなどの東ヨーロッパ諸国を社会主義化し、自国の衛星国とした。ソ連・ポーランド不可侵条約を一方的に破棄するとともに侵攻し、ポーランドの東半分を占領した。またバルト3国に圧力をかけ、ソ連軍の通過と親ソ政権の樹立を要求し、その回答を待たずに3国に進駐した。さらに親ソ政権を組織し、反ソ連派を粛清、或いは収容所送りにして、ついにこれを併合した。同時にソ連はルーマニアにベッサラビアを割譲するように圧力をかけ、1940年6月にはソ連軍がベッサラビアと北ブコビナに進駐し、領土を割譲させた。さらに隣国のフィンランドを冬戦争により侵略してカレリア地方を併合した。 さらに占領地域であった東欧諸国への影響を強め、衛星国化していった。その一方、ドイツ、ポーランド、チェコスロバキアからそれぞれ領土を獲得し、西方へ大きく領土を拡大した。 また、開戦前に併合したエストニア、ラトビア、リトアニアのバルト三国への支配、ルーマニアから獲得したベッサラビア(現在のモルドバ)の領有を承認させた。更にこれらの新領土から多くの住民を追放あるいはシベリアなどに強制移住させ、代わりにロシア人を移住させた。また、極東では日本の領土であった南樺太及び千島列島を占領し、領有を宣言した。さらに、1945年8月14日に連合国の一国である中華民国との間に中ソ友好同盟条約を締結し、日本が旧満州に持っていた各種権益のうち、関東州の旅順・大連の両港の租借権や旧東清鉄道(南満州鉄道の一部)の管理権の継承を中華民国に認めさせた。
第二次世界大戦によって大きな損害を蒙っていた西欧諸国において、共産主義勢力の伸張が危惧されるようになった。とくにフランスやイタリアでは共産党が支持を獲得しつつあった。戦勝国であったイギリスもかつての大英帝国の面影はなく、独力でソ連に対抗できるだけの力は残っていなかった。そのため、西欧においてアメリカの存在や役割が否応なく重要になっていった。1947年に入ると、3月12日にトルーマンは一般教書演説でイギリスに代わってギリシアおよびトルコの防衛を引き受けることを宣言した。いわゆる「トルーマン・ドクトリン」である。さらに6月5日にはハーヴァード大学の卒業式でジョージ・マーシャル国務長官がヨーロッパ復興計画(マーシャル・プラン)を発表し、西欧諸国への大規模援助を行った。こうして戦後アメリカは、継続的にヨーロッパ大陸に関与することになり、孤立主義から脱却することになった。
東欧諸国のうち、ドイツと同盟関係にあったルーマニア、ブルガリア、ハンガリー、スロバキアにはソ連軍が進駐し、共産主義勢力を中心とする政府が樹立された。当初は、「反ファシズム」をスローガンとする社会民主主義勢力との連立政権であったが、法務、内務といった主要ポストは共産党が握った。ヤルタ会談で独立回復が約束されたポーランドでも、ロンドンの亡命政府と共産党による連立政権が成立したが、選挙妨害や脅迫などによって、亡命政府系の政党や閣僚が排除されていった。こうした東欧における共産化を決定付けるとともに、西側諸国に冷戦の冷徹な現実を突きつけたのが、1948年2月のチェコスロバキア政変であった。またその前年の10月にはコミンフォルムが結成され、社会主義にいたる多様な道が否定され、ソ連型の社会主義が画一的に採用されるようになった。
沖縄の米軍基地強化と密接な関係がある中国の勢力拡大
1930年代から中華民国・南京国民政府と内戦(国共内戦)を繰り広げてきた中国共産党は、第二次世界大戦終結後に再燃した内戦で相次いで国民政府軍に勝利をおさめ、1949年4月には共産党軍が南京国民政府の首都・南京を制圧した。この過程で南京国民政府は崩壊状態に陥り、中国国民党と袂を分かって共産党と行動を共にしたり、国外へと避難したりする国民政府関係者が多数出た。その為、共産党は南京国民政府が崩壊・消滅したと判断し、同年10月に毛沢東が中華人民共和国の建国を宣言した。なお、崩壊状態に陥った南京国民政府は蒋介石の指導の下で台湾に撤退し(台湾国民政府)、引き続き現在にいたるまで中華民国と名乗っている。冷戦を経て現在中華民国を国家承認している国は30ヶ国未満であるが、二つの「中国」政府が並立する事態は台湾問題として東アジアの国際的政治問題となっている。
建国当初の政治を担ったのは、中国人民政治協商会議であった。この段階では共産党独裁体制は確立されておらず、「新民主主義論」のもと共産党、中国民主同盟、中国農工民主党、中国国民党革命委員会などの諸勢力が同会議の中心となった。1950年、土地改革法が成立して全国で土地の再配分が行われた。法の内容自体は穏健的なものであったが、地主に対して積年の恨みを抱いていた貧農などによって運動は急進化し、短期間で土地改革は完了した。
中華人民共和国の発足直後は、旧国民党、富裕層などによる反共・反政府運動が続発した。このため、「反革命活動の鎮圧に関する指示」が出され、大衆を巻き込んだ形で反政府勢力の殲滅を図った。1953年までに71万人を処刑、129万人を逮捕、123万人を拘束し、240万人の武装勢力を消滅させたことが、中国の解放軍出版社より出版された国情手冊に記されている。
1950年に中ソ友好同盟相互援助条約を結び、朝鮮戦争で北朝鮮を支援して参戦するなど、社会主義陣営に属する姿勢を鮮明にした。ただし、1954年のネルー・周恩来会談で平和五原則を示したこと、アジア・アフリカ会議(バンドン会議)にも積極的に関わったことに見られるように、常にソビエト連邦一辺倒なのではなく、第三勢力としての外交も行った。また、1956年のソ連共産党第20回大会においてフルシチョフが行った「スターリン批判」に対して、中国共産党は異なった見解(功績7割、誤り3割)を示した。これ以降ソビエト連邦との関係は徐々に悪化、のちの中ソ論争や中ソ国境紛争へとつながっていく。
国内では、1953年頃より社会主義化を本格的に進め始め、人民政治協商会議に代わって人民代表大会を成立、農業生産合作社を組織した。1956年に行った「百花斉放百家争鳴」運動にて知識人から批判をうけたため、これを弾圧するために1957年6月に批判的な知識人に対する反右派闘争を開始し、少なくとも全国で50万人以上を失脚させ、投獄した。1958年、毛沢東は大躍進政策を開始し、人民公社化を推進した。しかし、無計画に進められた大躍進政策は2000万人~4000万人以上とも言われる大量の餓死者を出して失敗に終わった。同じ頃、チベットの中国との同化を図り、「解放」の名目で軍事制圧し、ここでも数十万人の大虐殺を行なったとされる(根拠なし)。チベットの最高指導者、ダライ・ラマはインドに亡命し、未だ帰還していない。
毛沢東時代の中華人民共和国は、社会の共産主義化を推進した。建国直後の1949年にウイグル侵攻を行いウイグルを占領した。1950年にはチベット侵攻を行いチベットを併合した。1952年には朝鮮戦争に介入し、韓国軍と、アメリカ軍を主体とする国連軍による朝鮮統一を阻止した。毛沢東の指導のもとで大躍進政策と核開発を行ない、多くの餓死者と被爆者を出しながらも核保有国としての地位を確保する。1959年のチベット蜂起を鎮圧すると、1962年にはチベットからインドに侵攻した(中印戦争)。1974年には南シナ海に侵攻し、ベトナム支配下の西沙諸島を占領した(西沙諸島の戦い)。
沖縄の米軍基地強化と密接な関係があるアジアの冷戦
中国大陸では、戦後すぐにアメリカの支援する中国国民党と中国共産党が内戦を繰り広げたが、中国共産党が勝利し1949年に共産主義の中華人民共和国を建国。1950年2月に中ソ友好同盟相互援助条約を結んでソ連と連合した。
一方、中国国民党は台湾島に逃れ、アメリカの支援のもと大陸への反攻をねらった。また、中華人民共和国は朝鮮戦争に出兵することで、アメリカと直接対立した。すでにモンゴルではソ連の支援の下で共産主義のモンゴル人民共和国が1924年に成立していたが、戦後になって米英仏等が承認した。
日本が統治していた朝鮮半島は、ヤルタ会談によって北緯38度線を境に北をソ連、南をアメリカが占領し、朝鮮半島は分断国家となった。このため、1950年6月にソ連の支援を受けた北朝鮮が大韓民国へ突如侵略を開始し、朝鮮戦争が勃発した。朝鮮戦争には「義勇軍」の名目で中華人民共和国の中国人民解放軍も参戦し戦闘状態は1953年まで続いた。
フランス領インドシナでは、ベトナムの共産勢力が独立を目指し、第一次インドシナ戦争が起こった。1954年にフランスが敗北したため、ベトナムが独立を得たが、西側は共産主義勢力の拡大を恐れ、ジュネーブ協定によって北緯17度で南部を分割し、南側に傀儡政権を置いた。これは後のベトナム戦争の引き金となる。また、フランスとアメリカが強い影響力を残したラオス(1949年独立)、カンボジア(1953年独立)でも共産勢力による政権獲得運動が起こった。
これら共産勢力のアジア台頭に脅威を感じたアメリカは、1951年8月に旧植民地フィリピンと米比相互防衛条約、9月に占領していた旧敵日本と日米安全保障条約、同月にイギリス連邦のオーストラリア・ニュージーランドと太平洋安全保障条約(ANZUS)、朝鮮戦争後の1953年8月に韓国と米韓相互防衛条約、1954年に中華民国と米華相互防衛条約を立て続けに結び、1954年9月にはアジア版NATOといえる東南アジア条約機構(SEATO)を設立して西側に引き入れた他、中華民国への支援を強化した。また中東でも、アメリカをオブザーバーとした中東条約機構(バグダッド条約機構、METO)を設立し、共産主義の封じ込みを図った。
沖縄の米軍基地強化と密接な関係があった朝鮮戦争
1950年6月25日早朝、朝鮮人民軍は38度線を突破して南部への進撃を開始した。李承晩政権の朝鮮武力統一を未然に防止し、「南半部」を解放する、というのがその理由だった。
朝鮮人民軍は進撃をつづけ、1950年6月28日には韓国の首都ソウルを陥落させた。一方、在日米軍は7月1日、釜山に上陸して北上を開始し、沖縄駐留のB‐29が北朝鮮爆撃を開始した。また、6月27日には第七艦隊が台湾海峡に展開した。7月7日、国連は国連軍総司令部の設置を決定、東京の連合国軍最高司令官マッカーサーを国連軍総司令官に任命し、米軍を中心に16カ国からなる国連軍が編成された。
朝鮮人民軍の勢いは、国連軍参戦後もやまず、1950年8月下旬には、国連・韓国軍は、半島南東部の釜山・大邱などがある一角においこまれた。朝鮮半島の95%を北朝鮮が占領した。
9月15日、マッカーサーの指揮のもとに国連軍はソウル近郊の港町仁川への上陸を決行、韓国内の朝鮮人民軍を南北から挟撃した。
これを機に戦局は逆転し、1950年9月26日に国連軍はソウルを奪回、10月1日には韓国軍が38度線を突破し、つづいて7日に国連軍も同線を突破した。そしてこの日、国連総会は武力による朝鮮統一を承認した。国連・韓国軍はなおも北上して19日に平壌を占領。一部の部隊は26日に鴨緑江まで到達した。
しかしその前日、中国人民義勇軍が参戦して朝鮮人民軍とともに反撃に転じ、1950年12月4日に平壌を奪回、翌51年1月4日にはソウルを再占領した。これに対し、2月1日、国連総会は中国非難決議を採択、3月14日には国連・韓国軍はソウルを再奪回した。
戦線は38度線を境に膠着(こうちゃく)状態におちいり、打開策として中国本土やソ連領シベリア諸都市への原爆攻撃を主張したマッカーサーは、トルーマンにより、1951年4月11日に国連軍総司令官を解任された。以後も戦線膠着状態を打開するために、細菌弾、毒ガス弾も使用されたが、決定的な戦局の転換はおきなかった。
戦線が膠着状態になったのをみて、1951年6月23日、ソ連の国連代表マリクはラジオで休戦を提案、関係各国はこれを受けいれ、7月10日に開城を会場(10月に板門店に移動)として休戦交渉がはじまった。しかし、交渉は遅々として進まず、断続的に2年間におよび、ようやく53年7月27日板門店において、国連軍総司令官マーク・クラーク、朝鮮人民軍最高司令官金日成、中国人民義勇軍司令員彭徳懐の間で休戦協定が調印された(韓国は拒否)。
朝鮮戦争の死者と負傷者
国連・韓国軍側戦死者 50万人
負傷者 100万人
朝鮮人民軍・中国人民義勇軍戦死者 100万人
戦傷者 100万人
民間人の死亡者、行方不明者南北あわせて 200万人以上
普天間飛行場強化は共産主義勢力の封じ込み戦略のひとつであった
ソ連、中国、北朝鮮、北ベトナム、ラオス、カンボジアなどの共産勢力のアジア台頭に脅威を感じたアメリカは、日本、オーストラリア・ニュージーランド、韓国、中華民国への支援を強化し、共産主義勢力の封じ込みを図った。沖縄の軍事基地強化は共産主義勢力の封じ込み戦略のひとつであり、普天間飛行場も共産主義勢力の封じ込みを目的に拡大強化していった。
普天間飛行場は宜野湾市大山二丁目に所在しており、その面積は約480㏊である(宜野湾市野嵩・新城・上原・中原・赤道・大山・真志喜・字宜野湾・大謝名にまたがる)。これは宜野湾市の面積の約25%にあたる。那覇都市圏を構成する沖縄県の中でもっとも人口が過密な地帯の一部であり、普天間飛行場、キャンプ瑞慶覧(面積160㏊)、陸軍貯油施設(面積2㏊)を除くと使用可能な市域の面積が1294㏊となり、1995年の時点で人口密度は約6252人/㎢になった。
普天間飛行場は航空基地として総合的に整備されており、滑走路のほか、駐留各航空部隊が円滑に任務遂行できるための諸施設として、格納庫、通信施設、整備・修理施設、部品倉庫、部隊事務所、消防署、PX、クラブ、バー、診療所などが存在する。
普天間飛行場の歴史
1945年 沖縄戦の最中に、宜野湾一帯がアメリカ軍の支配下に置かれると、アメリカ陸軍工兵隊の発注により中頭郡宜野湾村(現・宜野湾市)の一部土地を接収し、2,400m級の滑走路を持つ飛行場が建設された。目的は日本本土決戦(連合軍側から見た場合ダウンフォール作戦)に備えるためであり、兵員及び物資の輸送に供することであった。
1945年 台風の直撃により建設途中の沖縄の各軍事施設が打撃を受ける。
1948年 リビー、デラ、グロリアの3台風が相次いで沖縄を直撃した。特に1949年6月のグロリアによる沖縄米軍基地全体の損害は8000万ドルに達した。その原因は基地施設がカマボコ兵舎に代表される簡易的な物が多く、天災に耐えるだけの恒久性を持っていないことにあった。これは戦後の軍事予算削減の影響を受けたものだったが、被害の大きさからより恒久的で台風や地震に耐えられる基地施設建設の機運が高まった。
1950年 朝鮮戦争勃発に伴い沖縄の戦略的価値が見直され、基地の恒久化を目的とした建設が進められることとなった。普天間もこれによる影響を受けていく。
1950年 GHQ下の極東軍司令部は1950年7月1日に遡及し、米軍が占領した民有地の借料の支払いを開始するように琉球民政府に指示した。
1953年 滑走路が2,800メートルに延長され、ナイキミサイルが配備された。
1955年 米軍は伊佐浜の土地を10万坪(立ち退き家屋32戸)接収すると通告し、住民は「土地取上げは 死刑の宣告」などのノボリを立てて反対した。しかし、7月19日の夜明け前、武装兵に守られたブルドーザーやクレーンにより家屋が取り壊され、32個136名の住民が住む家を失った。
1957年 陸軍から空軍へ管理を移管。
1960年 施設管理権がアメリカ空軍からアメリカ海兵隊へ移管された。民有地については、琉球政府が住民から土地を一括で借り上げたうえで米海兵隊に又貸しをし、軍用地料(基地・飛行場の土地賃借料)についてはアメリカ側から琉球政府に支払われたものを住民に分配する方法が採られた。
1969年 ●普天間第二小学校の創立。
1972年 沖縄返還に合わせて事務が琉球政府から日本政府(防衛施設庁那覇防衛施設局)に引き継がれ、日米地位協定第二条第一項に基づく米軍施設および区域と定義される。
1974年 嘉手納飛行場にP‐3Cが移駐されたことに伴い、その補助飛行場として使用するための滑走路を全面的に再整備。
●第15回日米安全保障協議委員会にて一部の無条件返還・移設条件付返還を合意。
1976年 ベトナム戦争終結後の海兵隊再編に伴い、上級司令部たる第1海兵航空団司令部が岩国よりキャンプ・バトラー(中城村)に移駐し、機能強化が図られた。
1976年 返還予定の中原区から航空機誘導用レーダーを移設。
1977年 ●10.9㏊を返還(12月15日代替施設として飛行場内に宿舎等を追加提供)。
1977年 ●0.3㏊を返還。
1977年 ●2.4㏊を返還。
1978年 ハンビー飛行場の返還に伴って格納庫、駐機場、隊舎等を移設。
1980年 米兵、一部一般市民の犯罪に対抗して周辺住民が組織していた自警団制度を廃止する。
1980年 格納庫等建物2600平方メートルを追加提供。
1981年 「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」に基づき第1種区域(住宅防音工事
対象区域)を指定(4740世帯)。
1983年 宿舎等建物11500平方メートルを追加提供。
1985年 ●宜野湾市消防庁舎用地として0.7㏊を返還。
1986年 隊舎として建物5,700平方メートル等を追加提供。
1987年 格納庫として建物5400平方メートル等を追加提供。
1992年 ●道路用地等として1.5㏊を返還。
1996年 ●普天間第二小学校校庭用地として0.9㏊を返還。
2000年 基地周辺の小学校において海兵隊員による英会話の実習を開始。
普天間飛行場は終戦の時にはすでにあった。1950年宜野湾の人口は1万5930人と少なく、普天間飛行場の周囲に人家はなかった。普天間飛行場の軍用地が返還されるようになると、返還された土地に人家や公共施設が建設されていった。
米軍には返還した土地を管轄する権利はない。普天間飛行場の周囲に人家や公共施設が増えていった原因は普天間飛行場の周囲を管轄していた宜野湾市の政策にあったといえよう。
「1955年7月11日、米軍は伊佐浜の土地を10万坪(立ち退き屋敷32戸)接収すると通告し、住民は『土地取上げは 死刑の宣告』などのノボリを立てて反対した。しかし、7月19日の夜明け前、武装兵に守られたブルドーザーやクレーンにより家屋が取り壊され、32個136名の住民が住む家を失った。伊佐浜の水田は収穫量も多く、戦前から『チャタンターブックヮ』(北谷のたんぼ)」と呼ばれる美田が広がっていました。戦時中も米軍の土地接収からもまぬがれ、戦後もかつてのように稲が植えられていました」
米軍が基地の拡大強化のためにフルドーザーと銃剣で強引に土地接収した行為として有名な話である。悪徳非道のようにみえる米軍の土地接収であるが、ブルドーザーと銃剣で強引に土地接収したのは共産勢力のアジア拡大を抑止する目的があった。
死者350万人以上という戦後最大の凄惨な戦争が朝鮮半島で起こった。ソ連、中国、北朝鮮、ベトナムなどの社会主義国家と韓国、台湾、南ベトナム、フィリピン、アメリカとの対立はいつ戦争が起こってもおかしくない状態にあり、アメリカ軍は早急にアジアの駐留軍を強化する必要に迫られていた。アジア全体の軍備強化のひとつとして伊佐浜の強制土地接収があった。
もし、アメリカ軍が沖縄・日本に駐留していなかったら、沖縄はチベットやウイグル地区のように中国の人民解放軍の武力によって占領されていたはずである。米軍基地がなければ平和で豊かな沖縄になれたと考えるのは非現実的な妄想だ。
土地を接収された伊佐浜の農民が土地闘争をするのは理解できるが、米軍が強引に土地接収した背景には第二次世界大戦後の世界を二分にしたソ連・中国の社会主義圏とアメリカ・ヨーロッパの資本・民主主義圏との熾烈な対立があったからであり、伊佐浜の土地接収を問題にするのなら背景にある中国、北朝鮮との対立、朝鮮戦争、ベトナム戦争、チベット侵略など社会主義圏と資本・民主主義圏の深刻な対立も問題にするべきである。
私が住んでいる読谷村でも大規模な土地接収があった。
海の近くにあった渡久地区の住民全員が通信基地トリイステイション設立のために立ち退きとなり、私が住んでいた比謝の隣に引っ越してきた。米軍は木や草が生えている広大な丘をブルドーザーであっというまに整地した。丘をあれよあれよという間に平地にしていったブルドーザーの威力に驚嘆したのを覚えている。ブルドーザーを警備しているガードマンが友達の父親だったので、父親の許しを得て、私たちはブルドーザーに乗ったりして遊んだ。整地された広大な広場は子供たちの絶好の遊び場であった。雪合戦ならぬ泥を丸めて投げ合う泥合戦もやった。
楚辺区も通信基地トリイステイション内にあったので全住民が強制的に立ち退きされて、米軍が整地した現在の場所に移った。
嘉手納弾薬庫では大湾、比謝橋、比謝、牧原、伊良皆、長田などは家をつくるのを禁じられ、すでにあった家は強制立ち退きをされた。トリイステイションや嘉手納弾薬庫は伊佐浜とは比べ物にならないほどの広大な土地である。しかし、伊佐浜のような抵抗運動はなかった。
唯一、強制立ち退きに抵抗して頑張った家が一軒だけあった。その家は幼稚園の時からの友達であるUの家だった。彼の父親は人民党員だった。だから最後まで立ち退きに抵抗したのだろう。彼の家のまわりには人家がなく、畑や雑草が茂っている広場が広がっていたので絶好な遊び場所だった。私は彼の家の近くでよく遊んだものだ。彼の家のある場所には伊佐浜のように米軍の設備を立てる目的はなかったので、米軍による銃とブルドーザーによる強制撤去はなかった。数年後に私の家から数百メートル離れた所に彼の家族は引っ越してきた。
何度も米軍による銃とブルドーザーによる強制立ち退きのことが話題にされるのだが、ほとんどは伊佐浜か伊江島である。伊佐浜と伊江島以外が話題になったことはない。もしかしたら強制立ち退きに抵抗したのは伊佐浜と伊江島だけだったかもしれない。
マスコミや知識人は銃とブルドーザーによる強制撤去は何度も話題にするが、辺野古が米軍基地を受け入れて、経済が奇跡的に発展したことはほとんど話題にしない。そして、辺野古の驚異的な経済発展の影響で土地闘争が崩れていった事実も話題にしない。
普天間第二小学校
宜野湾市立普天間第二小学校は、宜野湾市の北、国道58号線と国道330号線を結ぶ県道81号線の中ほどにあり、学校の北側には普天間三叉路があり、その周辺に普天間神宮や商店街などが立ち並んでいる。南側は米軍普天間飛行場とフェンス越しに向かい合っている。そのため、輸送機やヘリコプターの離着陸の騒音にさらされている。宜野湾村が市になった1962(昭和37)年ごろから人口が増え、中心地の普天間小学校の児童数も限界に近づいていたことから普天間第二小学校の建設は計画され、1969(昭和44)年に分離開校した。現在の校舎は1996(平成8)年に普天間飛行場を0.9㏊返還させて拡張した新校舎であり、オープン教室となっている。
普天間飛行場の危険性を問題にするときに必ず取り上げるのが普天間第二小学校である。子供たちが遊んでいる校庭の向こう側から数機の軍用ヘリコプターが一斉に飛び立つ映像はまるでベトナム戦争を見ているようで背筋が凍る。
非常にインパクトがある映像に多くの人は普天間飛行場の危険性を痛切に感じる。普天間飛行場からの騒音は教室内でも100ベシレル以上あり騒音で授業は中断されることも起こっている。普天間第二小学校の騒音被害を報じるたびに一日も早い普天間飛行場の撤去を訴える。
政治家、知識人、学者、教師、市民など多くの人たちが普天間飛行場の危険性を主張し移設を訴える。ただ、彼らのほとんどは日米政府が計画している普天間飛行場の辺野古移設には反対している。普天間飛行場の撤去を訴えている人の多くは「県外移設」を主張している。不思議なことに普天間第二小学校の移転を訴える人はほとんどいない。
普天間第二小学校の騒音問題を取り上げるマスコミも普天間飛行場の「県外移設」を問題にすることはあっても普天間第二小学校の移転を問題にすることはない。政治家、知識人、学者、市民運動家も普天間第二小学校の騒音被害や危険性を問題にしても移転を主張することはない。不思議な現象である。普天間第二小学校が騒音被害を受け、ヘリコプター墜落の危機を抱えているのなら、一日も早く普天間第二小学校を安全な場所に移転するのが最重要な課題であるし、普天間飛行場と違って宜野湾市政がその気になれば移転を実現することができる。ところが誰も移転を提案しない。普天間第二小学校の移転を提案するのはタブーなのだろうか。
普天間第二小学校は1969年に創立している。1969年といえば、ベトナム戦争が激しくなっていた頃である。前年の1968年には嘉手納飛行場からベトナムに向けて飛び立とうとしたB52重爆撃機が墜落炎上し、大爆発を起こして県民を恐怖のどん底に落とした。その年に「命を守る県民共闘会議」が結成され、県民の反基地運動が一番盛り上がった時であった。その時に宜野湾市は普天間第二小学校を普天飛行場の金網沿いにつくったのである。普天飛行場の金網沿いにつくれば騒音被害、飛行機墜落の危険があるのは当然である。それを承知の上で宜野湾市は普天間飛行場の金網沿いに普天間第二小学校を設立したのだ。信じられないことである。
子どもの人権を踏みにじる行為をしたのは宜野湾市政である。非難されるべきは宜野湾市政であり米軍ではない。
米軍の飛行機が墜落炎上する恐れを一番感じている時に宜野湾市は普天間飛行場の金網沿いに普天間第二小学校をつくった。人間の常識としてありえないことである。子どもたちを基地被害の人身御供にして、基地の危険性をアピールするために普天間第二小学校をつくったのではないかと疑ってしまう。
普天間第二小学校の移転問題
1969年当時は普天間第二小学校周囲には空き地が多かった。普天間飛行場から離れた場所でも小学校をつくることは楽にできたはずである。それなのに宜野湾市政はわざわざ金網沿いに小学校をつくった。なぜ、金網沿いにつくったのだろうか。学校は広い敷地が必要であり、土地購入代金の負担が大きい。そのために学校をつくる場所はできるだけ土地代が安い所を選ぶ傾向にある。だから、住宅街からは遠く離れた土地代が安い場所に学校をつくることが多い。人家の少ない場所に学校ができ、その後に人家が増えていくパターンが普通である。沖縄国際大学も那覇市の土地が高いので土地の安い普天間飛行場の近くにつくったという経緯がある。そのように考えると普天間第二小学校を普天間飛行場の金網沿いにつくったのは、その土地が安かったからであろう。普天間飛行場の金網沿いにつくれば子どもたちの騒音被害や飛行機墜落の危険は明らかであった。それなのにつくった。子どもの人権よりお金の節約なのである。
読谷村にも金網に囲まれた小学校がある。字大木の西外れにある古堅小学校である。私が在籍していた頃は古堅小中学校であり、私は9年間在籍した。古堅小学校は西と南が金網でL字状に囲まれていて、ボール遊びをするとボールが金網の中に入ることが度々あった。ボールを取りに金網を飛び越えて基地内に何度も侵入した経験がある。私たちにとって基地侵入は日常茶飯事であった。基地侵入は犯罪であるが、それをやらなければならなかったのが金網に囲まれた学校の生徒の宿命であった。金網に張り付いて移動する競争や誰が金網を早く飛び越えるかの競争もやった。子供は周りのものを全て遊びにする。たとえ、米軍基地でも。
普天間飛行場の金網沿いに小学校をつくるということは騒音が大きいし、ヘリコプターの墜落の可能性があるのははっきりしている。それに金網を目の当たりした学校生活は生徒に閉塞感をもたらす。米軍基地の金網沿いに学校をつくるのは教育上非常に悪いことである。
普天間飛行場の金網沿いに小学校をつくったということは、子どもの人権をないがしろにした宜野湾市の市長、議員、市民であったということである。
1987年(昭和57)に、普天間第二小学校から200メートルしか離れていないところに米軍ヘリが不時着炎上した。当時、宜野湾市長だった安次富(あしとみ)盛信さん(79)によると、これまでも爆音被害に悩まされていたが、炎上事故を受け、小学校に米軍機が墜落しかねないとの不安が広がり、移転を望む声が地域の人たちから沸き上がった。
安次富さんらは移転先を探したが確保できなかったため米軍と交渉した。約1キロ離れた米軍家族用の軍用地のうち8千坪を校舎用に日本に返還することで合意。防衛施設庁とも協議して移設予算も確保した。
ところが、市民団体などから「移転は基地の固定化につながる」などと抗議が殺到した。安次富さんは「爆音公害から少しでも遠ざけ危険性も除去したい」と説明したが、市民団体などは「命をはってでも反対する」と抵抗したため、計画は頓挫した。
その後、昭和63年から平成元年にかけ、校舎の老朽化で天井などのコンクリート片が落下して児童に当たる危険性が出たため、基地から離れた場所に学校を移転させる意見が住民から再び持ち上がった。だが、やはり市民団体などに「移転せずに現在の場所で改築すべきだ」と反対され、移転構想はストップした。それどころか普天間飛行場の0・9ヘクタールを開放させて、学校の敷地を拡大した。普天間飛行場から離れるどころかますます普天間飛行場に食い込んだのである。信じられないことである。
1968年に嘉手納飛行場でB52重爆撃機が墜落炎上爆発した翌年に普天間第二小学校をつくり、小学校から200メートル離れた場所でヘリコプターが不時着炎上したのに移転はしなかった。老朽化した時にも移転の希望が持ち上がったが結局は移転しなかった。普天間飛行場の金網沿いに学校をつくれば騒音被害は当然起こることである。宜野湾市は騒音被害が起こるのを知りながら金網沿いに普天間第二小学校をつくったのだ。1969年から40年以上も移転をしないで普天間第二小学校の子供たちを騒音被害にさらしてきたのは宜野湾市政である。宜野湾市政の責任は大きい。
普天間飛行場の騒音が子供たちの人権を犯していると主張する人は多いのに、宜野湾市政を非難する人はいない。普天間飛行場の「県外移設」を主張する人は多いが普天間第二小学校の移転を主張する人はほとんどいない。なにかがおかしい。とてもおかしい。
普天間第二小学校移転問題と普天間飛行場移設問題は別の問題であり、子どもの人権を守るために普天間第二小学校は一日も早く安全な場所に移転するべきである。安次富さんが移転しようとしていた外人住宅地は現在使用していない。その場所に一日も早く移転するべきである。普天間第二小学校の移転より普天間飛行場の移転が先であると主張するのは頭がおかしいというしかない。
普天間飛行場のクリアゾーンに人が住んでいるのは誰の責任か
クリアゾーンとは滑走路の両端から900メートルは航空機事故が起きる可能性が高いとして土地利用を禁じた場所のことである。クリアゾーンはアメリカは設定しているが、日本は設定していない。
宜野湾市の普天間飛行場では「クリアゾーン」の中に、住宅約800戸、公共施設、保育所、病院が18カ所存在し、約3600人が暮らしている。世界一危険な飛行場と呼ばれている所以である。なぜ、「クリアゾーン」の中に3600人もの人たちが住むようになったのだろうか。それは米軍の性なのだろうか。
しかし、米軍が管轄できるのは基地内である。普天間飛行場の外は米軍が管轄することはできないし、アメリカの法律を適用することもできない。普天間飛行場の外に適用されるのは日本の法律であり、人を住まわすか住まわせないかを判断するのは宜野湾市政である。宜野湾市政が普天間飛行場周辺をクリアゾーンとして設定し、人が住むのを禁じていれば普天間飛行場のクリアゾーンに人が住むことはなかった。しかし、宜野湾市政はクリアゾーンを設定しないどころかクリアゾーンに小学校、公共施設、保育所、病院などをつくり、住宅も約800戸の建設を許可し、3600人もの人たちが住むようにしたのである。
普天間飛行場のクリアゾーンに公共施設、保育所、病院、住宅をつくらせたのは米軍ではない。宜野湾市政である。宜野湾市政は軍用地が返還された場所にどんどん公共施設、保育所、病院、住宅をつくらせた。もし普天間飛行場の周辺にアメリカ政府の方針を反映させていたならクリアゾーンに公共施設、保育所、病院の建設を許可しなかったはずである。クリアゾーンに建設を積極的にやったのは米軍ではなく宜野湾市政であった。クリアゾーンに住宅約800戸、約3600人の住民が暮らしているのは米軍が望んだことではなく、宜野湾市政が望んだことであり、宜野湾市政の方針があったから、米国では危険地帯として人が住むのを禁じているクリアゾーンに約3600人もの人々が住んでいるのである。
宜野湾市政には普天間飛行場の騒音や危険から住民を守る人権擁護の思想がなかったということであり、クリアゾーンを設定する意思がなかったということである。
宜野湾市は普天間飛行場の金網沿いに普天間第二小学校をつくった。普天間第二小学校をつくったのは宜野湾市政の方針であり、沖縄国際大学をつくらせたのも宜野湾市政の方針である。普天間第二小学校や沖縄国際大学を設立したことに米軍は一切関係していない。
普天間飛行場周辺の騒音被害や危険性は以前からあったことであり、宜野湾市政はそのことを知っていながら普天間飛行場のクリアゾーンに人を住まわせたのである。騒音被害や事故の危険性を無視したのは宜野湾市政である。
普天間飛行場の移設問題
1996年に3人の米兵による婦女暴行事件をきっかけに反米・反基地運動が高まった。危機感を持った日米両政府は8000人の海兵隊のグアム移転と嘉手納飛行場以南の米軍基地の撤去と普天間飛行場の辺野古移設を発表した。しかし、辺野古移設が反対運動の抵抗に会い計画は難航している。
世界一危険な普天間飛行場は三通りの移設方法が持ち上がっている。国外移設、県外移設、辺野古移設である。
沖縄の反戦・平和運動は「沖縄に米軍基地があるから戦争に巻き込まれる」という理由で沖縄の米軍基地の撤去を主張してきた。米軍基地の撤去とは国外に撤去するということである。米軍基地がなければ沖縄は平和で豊かな社会になると反戦・平和運動家や革新政治家は主張してきた。
一方、米軍基地は中国の脅威を抑止するためには必要であるし、基地経済は県経済を潤すと考える保守系政治家は辺野古移設を主張してきた。
革新系の普天間飛行場の閉鎖又は国外移設の主張と保守系の辺野古移設の二分した主張が続いていたが、新たに「県外移設」の主張が加わった。
「できるなら国外、最低でも県外移設」を選挙公約にした民主党は選挙戦に圧倒的に勝利した。民主党が与党になったので、「できるなら国外、最低でも県外移設」の公約が実現するものと県民は期待した。首相になった鳩山氏は「できるなら国外、最低でも県外移設」を公言した。国外移設候補はグアムであり、グアム移設か県外移設で揺れたが、次第にグアム移設が困難であることが明確になるにつれて「最低でも県外移設」と発言し続ける鳩山元首相に県民の期待が集中し、「県外移設」は盛り上がった。民主党の国会議員のほとんどは与党になった途端に「県外移設」を口にしなくなったが、鳩山元首相だけは「県外移設」が実現できると思い込み、移設場所を必死に探した。色々な候補地があがったが、ほとんどの場所が小泉元首相時代に移設を断念した場所であり、鳩山元首相の「県外移設」は頓挫した。そして、「辺野古移設」に戻った。県民の多くが鳩山元首相の辺野古回帰に落胆した。そして怒った。
鳩山元首相の「県外移設」は頓挫したが、県民の「県外移設」への要求は熱いままである。
鳩山元首相は沖縄の過重な基地負担を軽減するとして、いわゆる沖縄への同情から普天間飛行場の「県外移設」を主張してきたが、市民の側からは「県外移設」は当然の権利とする理論が登場した。それが構造的差別論である。
国土の1パーセントにも満たない沖縄に、日本の米軍基地の75パーセントが集中しているのは日本政府が沖縄を差別しているからだという考えが構造的差別論である。
沖縄の差別をなくすために沖縄の米軍基地は日本全体で平等に負担するべきであり、そのためにも普天間飛行場は本土に移設するべきであると構造的差別論者は主張する。構造的差別論は「沖縄の負担を軽減する」という思いやり的な考えに対して「県外移設」は沖縄の構造的な差別を解消するための正当な要求であり、沖縄の権利であると主張している。
国外移設運動の歴史
1968年11月19日に、嘉手納飛行場でB52の墜落炎上事故が起こり、沖縄住民にあらためて米軍基地の危険性、嘉手納弾薬庫の核爆弾の恐怖を喚起させた。その年の12月7日に、「生命を守る県民共闘会議」が結成され、スローガンに「命どぅ宝」を掲げた。「なによりも一番大事なのは命であり、戦争は武装した人間同士が殺りくを繰り返すこと、あるいは武器を手にした人間が武器を持たない人間の命を奪うことであり、戦争は愚かで悲しく、絶対に許されない行為である」と「生命を守る県民共闘会議」を中心に沖縄の反戦・平和運動は沖縄の米軍基地のすべてを撤去するように主張し続けてきた。国外移設を主張することは反戦・平和を主張することと同じことであった。反戦平和・米軍基地撤去運動は共産党、社民党、社大党の革新政党や沖縄教職員組織等が中心となって推進してきた。
普天間飛行場の国外移設候補地はグアムだった。社民党はグアム移設に積極的だったが、現地調査では、沖縄本島の半分以下の面積であるグアム島に、すでに面積の3分の1をアメリカ軍基地が占めていて、普天間飛行場を移設するのは困難であることや、グアム島ではヘリコプターがアジアの緊急事態に対応することができないという米軍の主張もあり、グアム移転は困難視された。「国外移設」の主張は次第に萎んでいった。
県外移設運動の歴史
県外移設を最初に検討したのは小泉元首相であった。辺野古海上移設は移設反対派の激しい抵抗で断念せざるをえなかった。辺野古海上移設を断念した小泉元首相は県外に普天間飛行場の移設場所を探した。しかし、一年近く県外移設場所を探したが見つけることはできなかった。小泉元首相は県外移設を断念して辺野古の陸上に移設することにした。辺野古移設の検討は小泉首相の退陣後も続けられ、最終的にV字滑走路にすることで県側、名護市の了承を取った。ところが移設工事をする前に、自民党政権から民主党政権に変わり、新しい政権の長となった鳩山元首相は「最低でも県外移設」を公約にした。「県外移設」に県民の期待が集まったが、結局は移設先を見つけることができなくて辺野古移設に戻った。
自民党だけでなく、野党のときは国外・県外を主張していた民主党も政権を握ったら辺野古移設になった。
しかし、沖縄県民の「県外移設」への期待は熱いままである。「県外移設」を望むマスコミや知識人は「県外移設」を正当化する構造的差別論を主張するようになった。沖縄の構造的差別をなくすために普天間飛行場は本土に移設するべきだというマスコミや知識人や政治家の主張は根強い。
沖縄の構造的差別は本当か
1パーセントの土地に75パーセントの米軍基地があるのは日本政府の沖縄への構造的差別である。構造的差別を解消するためには沖縄の米軍基地は全国で平等に負担するべきであり、普天間飛行場は本土に移設するべきであると主張しているのが構造的差別論である。構造的差別論には日本を守っているのは米軍であるという印象が強い。しかし、日本を守っているのは米軍だけではない。自衛隊がいる。全国の自衛隊員は22万8536人である。構造的差別を主張している人たちは自衛隊の存在を計算に入れていないように感じる。
➀ 航空自衛隊の主要装備
F-15戦闘機201機(F15運用国ではアメリカに次いで第2位の保有数である)、F‐2戦闘機80機、F‐4戦闘機約64機、合計345機余と、E-2早期警戒機が13機、E‐767早期警戒管制機が4機と、早期警戒機の数も多く、またKC‐767空中給油機が4機と自衛隊の防空能力は高い。
➁ 海上自衛隊の装備
通常動力型潜水艦16隻、護衛艦約50隻、ヘリコプター、哨戒機、電子戦機合計で約300機保有する。
➂ 陸上自衛隊の装備
戦車2、542両、装甲車両3、081両、自走砲1、307両、火砲・ロケット1、651台、誘導弾1、369個、ヘリコプター1、138機、航空機311機。
軍事力は在日米軍よりはるかに自衛隊のほうが勝っている。日本の防衛は自衛隊と在日米軍のコンビネーションでなりたっているのであって米軍だけが日本を防衛しているわけではない。本土の自衛隊基地の存在を無視して、1パーセントの土地に75パーセントの米軍基地があると、在日米軍だけが日本を防衛しているように考えるのは間違いである。むしろ、米軍よりもはるかに自衛隊のほうが日本を防衛している。
日本の軍事力は自衛隊と在日米軍の合計で判断するべきであり、沖縄の米軍基地は日本全体の自衛隊基地と米軍基地の配置のありかたを問題にするべきである。
自衛官の総計 22万8536人
本土所在米軍人 2万2078人
在沖米軍人 2万2772人 (自衛隊比10%)
在日米軍合計 4万4850人 (自衛隊比19・6%)
自衛隊員+米軍人 27万3386人
米軍人の全体比 16%、
在沖米軍人の全体比 8・3%
在日米軍だけの比率でみれば本土所在米軍人2万2078人、在沖米軍人2万2772人であり、在沖米軍人の比率は約50%である。自衛隊も合わせた全体の人数の比率からみれば在沖米軍人は8・3%である。
8・3%でも1%の面積しかない沖縄には比率が高いといえるが、沖縄に米軍基地が集中したのには、米軍が沖縄に上陸した時に戦争が終わったという歴史的な偶然と、対立していたソ連、北朝鮮、中国、ベトナムなどアジアの社会主義圏とは地理的に扇の要の位置にあるという軍事的な必然もあった。
日米政府は嘉手納飛行場以南の米軍基地は返還し、8000人の海兵隊をグアムに移動すると提案したのだから、沖縄の米軍基地は半減し、在沖米軍人の全体比は5・4%になる計算になる。それを考慮に入れると、米軍基地が沖縄に集中しているとは言えない。皮肉なことに米海兵隊と基地削減計画を阻んでいるのが辺野古移設反対運動である。
沖縄に米軍基地があるから日本の安全が守られてきたと、まるで米軍だけが日本を守っていると考えるのは間違った考えである。自衛隊が22万8536人も居て、在沖米軍人が2万2772人しかいないことから分かることである。
アジアに駐留している米軍が日本を守っているのは確実であるが、たった、2万2772人の在沖米軍だけが日本を守っているというのは大げさである。日本と沖縄を防衛しているのは自衛隊と在日米軍以外にアジアに駐留している米軍とのコンビネーションである。
軍事ジャーナリストの惠隆之介氏によると、米軍専用基地は確かに75%が沖縄にあるが、全国にある米軍基地を自衛隊との共用基地も含めて計算すると沖縄の米軍基地は24%にしかならないという。
構造的差別論は、米軍だけが日本を守っているという考えであり、米軍が本土で自衛隊と共同使用している基地を計算に入れていないし、自衛隊を日本を守る軍隊として計算に入れていない。構造的差別論は事実を正確に把握していない理論である。
構造的差別論は反戦・平和主義ではない
1968年に「命をまもる県民共闘会議」を結成して以来、革新政党や教職員組合等は平和憲法を重んじ、「命どぅ宝」をモットーとした反戦・平和運動を展開し、米軍基地の撤去を主張し続けてきた。反戦・平和主義による米軍基地撤去とは米軍基地の国外移設のことであり、国外移設には反戦・平和主義が根底にある。
一方、普天間飛行場の「県外移設」の主張は日本政府の沖縄への構造的差別を問題にしている。沖縄だけがいつまでも基地の過重な負担を背負い続ける構図は「構造的差別」であり、普天間飛行場の辺野古移設は沖縄への構造的差別を続けることになる。構造的差別をなくすために普天間飛行場は本土に移転するべきだと主張している。構造的差別論は米軍基地が沖縄に集中していることを問題にしているのであり、米軍が日本に駐留することは容認している。日本の米軍駐留を容認している構造的差別論は反戦・平和主義を放棄したことになる。
○ 反戦・平和主義=日本の米軍基地を認めない。米軍基地の国外撤去。
○ 構造的差別論 =日本の米軍基地を容認、米軍基地の日本全体への平均的な配置。
県外移設論は米軍基地を日本国内に移設することであり、日本国内から米軍基地を撤去するという考えはない。構造的差別論は米軍基地の日本国内での現状維持を認めている。「米軍基地があるから戦争に巻き込まれる」「沖縄・日本が戦争のない平和で豊かになるためには米軍基地は日本からなくすべきである」「命どぅ宝」という反戦・平和主義の思想は構造的差別論にはない。構造的差別論は反戦・平和主義ではない。極言すると単純平和主義である。
共産党、社民党は平和憲法遵守の立場であり、全てのアメリカ軍が日本から撤去することを主張している。「県外移設」を主張することは米軍基地の「本土受け入れ」に賛成することであるから、共産党・社民党が「県外移設」を主張することはありえない。「国外移設」は反戦・平和主義であり、「県外移設」は反戦・平和主義ではない。「国外移設」運動と「県外移設」運動は性質が違う運動であり、相容れない運動である。
普天間飛行場の国外移設=グアム移設は可能か
普天間飛行場の国外移設候補地になったのはグアムである。ハワイやアメリカ本国も候補地に上ったが、アジアから遠すぎるのですぐに候補からはずれた。グアム移設に積極的だったのが社民党と共産党だった。アメリカ政府はアジアから遠く、緊急事態に対応できないという理由で普天間飛行場のグアム移設に反対した。
すでにグアム島の面積の3分の1をアメリカ軍事基地が占めている。島の北部には3,000m級滑走路が2本あるアンダーセン空軍基地が存在する。沖縄本島に駐屯しているアメリカ海兵隊8,000人がグアムに移駐する予定であり、それに加えて普天間飛行場の移設となるとグアムの負担は大きい。沖縄本島の半分しかないグアムでは普天間飛行場の移設は困難であることが明確になってきた。
沖縄の構造的差別を主張する市民団体は、日本政府に差別されている沖縄民族、アイヌ民族と同じようにグアムの先住民・チャモロ族もアメリカに差別されている民族であると主張し、チャモロ族の、「米軍増強は、われわれが現在甘んじている政治的立場とあいまって、先祖代々受け継いだ文化と民族の誇りに対するジェノサイド(大虐殺)をもたらす」という主張に同調し、普天間飛行場のグアム移設に強く反対している。
アメリカ政府の反対、グアム現地の反対に加え、沖縄の構造的差別を主張する市民団体の反対もあり、グアム移設の主張は小さくなっている。
グアム移設は不可能である。
普天間飛行場の「県外移設」は可能か
県民の多くは「県外移設」に賛成している。仲井真知事や沖縄自民党は「県外移設」を公約にしている。沖縄民主党も「県外移設」を主張し、多くの知識人も「県外移設」を主張している。「県外移設」に反対の立場であるはずの共産党や社民党も「県外移設」に表だって反対はしていない。
沖縄の大勢は「県外移設」であるが、県民の大多数が賛成するだけでは「県外移設」を実現することはできない。県外移設が実現する絶対的な条件がある。普天間飛行場の受け入れを承知する県がなければならないことだ。移設場所の住民が賛成し、住民が住んでいる市町村が賛成し、県が賛成し、アメリカ政府が賛成して初めて普天間飛行場の移設は実現する。普天飛行場受け入れに住民、市町村、県が賛成するところが本土にあるとは思えない。
県外移設を最初に検討したのは小泉元首相であった。辺野古海上移設は困難だと考えた小泉元首相は県外に普天間飛行場の移設場所を探した。しかし、見つけることはできなかった。本土への移設を断念した小泉元首相は辺野古の陸上に普天間飛行場を移設する方針に転換した。小泉元首相の意思を受け継いだ自民党首脳は紆余曲折を経ながらV字滑走路の飛行場にすることで辺野古、県、名護市の了承を得た。しかし、移設工事を始める前に、政権が自民党から民主党に変わり、新しく首相になった鳩山氏は「最低でも県外移設」を公約にした。しかし、鳩山元首相は本土に普天間飛行場を移設できる場所を見つけることができなくて辺野古移設に戻った。
自民党・民主党の両政府の最高権力者である首相が県外に移設場所を求めながら結局は見つけることができなかった。この事実は重い。この事実は「県外移設」は不可能に近いということを示している
「県外移設」を主張する沖縄の政治家や知識人は多い。しかし、彼らは自民党、民主党の両政府の首相が移設場所を見つけることができなかった事実を軽視している。彼らは政府や官僚が「県外移設」を真剣にやろうと思えば実現すると主張し、「県外移設」ができないのは政府や官僚が真剣に取り組んでいないからだと主張している。多くの県民は沖縄の政治家や知識人の影響で政府がその気になれば「県外移設」ができると信じている。本当にそうだろうか。
馬毛島は鹿児島県にある無人島である。住民の住んでいる島から12キロメートル離れた場所に馬毛島はある。馬毛島は米軍空母艦載機の離着陸訓練の候補地になっていた。完成すれば嘉手納飛行場の戦闘機も馬毛島で離着陸訓練をやる予定であった。
「馬毛島」のある鹿児島県西之表市の市議会議員らが来県し、嘉手納飛行場を視察した。市議たちは嘉手納飛行場の戦闘機のごう音に驚いた。嘉手納飛行場を視察した市議たちを中心に馬毛島の離着陸訓練への反対運動が広がった。県や地元4市町の反対によって馬毛島の滑走路の建設は中止している。
12キロも離れている無人島の「馬毛島」で戦闘機の離着陸訓練する滑走路を造ることでさえ反対するのが本土の住民たちである。沖縄の米軍基地反対派の人たちは米軍基地被害のひどさや海兵隊員の恐ろしさを本土の人たちに発信し続けてきた。だから本土の住民は米海兵隊がやってくることに恐怖し拒否反応が起こる。
普天間飛行場の大きさは馬毛島の離着陸訓練用滑走路の比ではない。普天間飛行場移転となると馬毛島と違って海兵隊もやってくる。住民の住んでいる場所から12キロメートルも離れている馬毛島の離着陸訓練用滑走路建設にさえ反対するのだから、普天間飛行場の移設ならもっと激しい反対運動が起こるだろう。西之表市の市議会議員らの「馬毛島」の陸上着陸訓練滑走路建設への拒否反応をみれば、本土の住民が普天間飛行場を受け入れるのは不可能であることがわかる。
普天間飛行場の本土移設にはもうひとつ重要な問題がある。普天間飛行場は海兵隊が使用する飛行場であるから海兵隊が駐留している沖縄から離れすぎた場所に移設することはできない。普天間飛行場の移設先は距離が限られている。与論島から徳之島、九州南部あたりが限界といわれている。しかし、その場所で受け入れ可能な場所がないのはすでに調査済みである。移設ができないという結論が出た地域に移設場所を探すことは不可能に近い。
県外移設論者たちのずるさ
政府は小泉首相時代と鳩山首相時代に「県外移設」をやろうとしたが移設場所を探すことができなかった。二度も「県外移設」に失敗した政府は「県外移設」を諦めて辺野古移設一本に絞っている。政府が今後「県外移設」を模索することはないだろう。日米両政府は辺野古に移設するまでは普天間飛行場を維持するつもりでいる。沖縄側が「県外移設」を政府に訴えても政府が動くことはありえない。
「県外移設」を断念した政府に「県外移設」を要求しても平行線が続くだけで、時間が無駄に過ぎていくだけである。
「県外移設」を実現する残された方法はひとつしかない。「県外移設」を主張する政治家、団体、識者、マスコミ等が一致団結して「県外移設場所」を探すことだ。移設候補地は国内だから情報は集めやすいし移設候補地に行き来するのも自由だ。「県外移設」を否定している政府に頼らないで、自分たちで移設先を探す以外に「県外移設」を実現する方法はない。
「県外移設」を主張する政治家、団体、識者、マスコミ等が「県外移設」を実現する会を結成して、全力で移設できそうな場所を調査するのが「県外移設」実現のための第一歩である。普天間飛行場の移設候補地を見つけたら、候補地の住民を説得して移設を承諾してもらう。住民の承諾を得たら政府と交渉する。このやり方が「県外移設」を実現する唯一の方法である。
しかし、今まで、「県外移設」を主張している国会議員、県知事を頂点とする沖縄の政治家や団体、マスコミ等が、政府は頼りにならないから自分たちで県外移設場所を探すと発言したことは一度もない。政府が「辺野古移設しかない」と断言しているのにもかかわらず、沖縄の「県外移設」を主張する人たちは自分たちで移設先を探そうとはしない。自分たちで移設場所を探そうとしないのはなぜか。理由ははっきりしている。国会議員、県知事を頂点とする沖縄の政治家や団体、マスコミ等は「県外移設」ができないという現実を知っているからである。馬毛島の例があるように本土の住民は米軍基地への拒否反応は強い。もし、「政府が探さないなら自分たちで探す」と宣言して県外移設場所を探したら、県外移設場所がないことを自分たちで明らかにしてしまうことになる。そして、「県外移設」の運動に自分たちで終止符を打ってしまう。国会議員、県知事を頂点とする沖縄の政治家や団体、マスコミ等はそのことを知っているのだ。だから、自分たちで普天間飛行場の県外移設場所を探すとは絶対に口に出さないのだ。
「県外移設」を主張し続けるためには、自分たちで移設場所を探さないことである。だから、誰ひとりとして「県外移設」場所を自分たちで探そうとは言わない。自分たちで探すとは言わないで、政府に「県外移設」を要求している間はいつまでも「県外移設」を主張することができ、県民の支持を集めることができる。「県外移設」を主張している人たちのずるさを感じる。
普天間飛行場の受け入れに賛成する住民は本土にはいない。普天間飛行場の「県外移設」は不可能である。
政治評論家の岡本行夫氏は普天間飛行場の県外移設は可能であるが、実現には20年かかると言っている。気の遠くなるような時間であり、実現しないのと同じである。20年後ならアジア全体が自由貿易地域になり、領土争いや武力対立は解消の方向に進んでいるだろう。中国の民主化もかなり進み、中国の脅威はゼロに近くなっているだろうから、沖縄の米軍基地は撤去しているか撤去の方向に進んでいるだろう。
辺野古移設は可能か
稲嶺名護市長は、辺野古移設は不可能といい、仲井真知事も辺野古移設は不可能と言っている。仲井真知事が辺野古移設は不可能であるという根拠は辺野古移設反対派の稲嶺氏が名護市長に当選し、市議会も革新系の議員が過半数になったからである。自民党である仲井真知事の本心は辺野古移設に賛成である可能性は高い。
辺野古が過疎化するのは時間の問題である。それなのに、県も名護市も辺野古の過疎化を食い止める政策を示していない。過疎化阻止を県にも名護市にも頼ることができない辺野古区民が選択したのが普天間飛行場の辺野古移設である。辺野古に米軍のヘリコプター飛行場ができれば雇用が増える。米兵相手の商売も増える。辺野古飛行場を見学する観光客も増えるだろう。道の駅をつくれば辺野古飛行場を見学に来た人たち相手の商売もできる。将来、アメリカ軍が撤去すれば辺野古の飛行場を民間飛行場として使い、やんばるに観光客を直接呼ぶことができる。
辺野古の過疎化を食い止める方法が普天間飛行場の移設だと辺野古区民は考え、普天間飛行場の辺野古移設に賛成している。
地元の辺野古区民が移設に賛成しているのだから辺野古移設は可能である。全国で普天間飛行場の受け入れに賛成しているのは辺野古だけである。辺野古以外に普天間飛行場を移設できる場所はない。辺野古移設は可能である。
辺野古は米軍基地を受け入れて繁栄した過去がある
「銃器とブルドーザー」で土地接収している米軍に立ち向かい、島ぐるみの土地闘争が盛り上がっていた1956年に、辺野古は軍用地受け入れを決意した。その時の辺野古は久志村であり、名護市に併合されていなかった。
「どんなに反対しても銃とブルドーザーで土地を接収されるなら、むしろ受け入れを表明して、こっちの要求も聞いてもらおう」というのが辺野古が軍用地受け入れを決意した理由である。それは苦渋の選択であった。
一 農耕地はできる限り使用しない。
二 演習による山林利用の制限。
三 基地建設の際は労務者を優先雇用する。
四 米軍の余剰電力および水道の利用。
五 損害の適正保障。
六 不用地の黙認耕作を許可する。
辺野古はこのような要求を受け入れの条件にして米軍と交渉した。
「銃とブルドーザー」による米軍の土地接収については何度も報道され、体験談も数多く発表されている。米軍の強引な土地接収に対して島ぐるみの土地闘争が盛り上がったこともマスコミは頻繁に報道している。しかし、土地闘争のその後についてはほとんど報道していない。
苦渋の選択で軍用地を受け入れた辺野古に思わぬ奇跡が起こる、それは辺野古の史上空前の繁栄であった。人口も4倍に増えた。辺野古の繁栄は他の地域に影響を与え、基地を誘致する地域も現れた。
辺野古の繁栄は土地闘争にも影響を与え、米軍の土地接収に断固反対を貫く意見と地元や地主が受け入れるなら米軍と妥協点を探っていこうとする意見に分かれた。島ぐるみ闘争は分裂し、やがて衰退していく。
この事実についてはNHK取材班が出版した「基地はなぜ沖縄に集中しているか」に詳しく書かれている。この本を読むまで辺野古が米軍基地を受け入れた過去があったことを知らなかったし、土地闘争が分裂し衰退していったことも知らなかった。
今も中国・北朝鮮と周辺国との緊張状態は続いている
2010年3月に韓国軍の艦船が沈没させられ、11月には北朝鮮が黄海の南北境界水域に近い韓国の延坪島を砲撃した。北朝鮮と韓国は停戦状態であって、戦争が終結したわけではない。まだ緊張状態が続いている。米軍が韓国に駐留していることが北朝鮮への抑止力となっている。
沖縄がアメリカから日本へ施政権が移り、日本が沖縄を防衛するようになると、領海の防衛力の弱い日本の弱点を見抜いて中国漁船団が尖閣諸島の領海で漁をするようになった。中国漁船の振る舞いは横暴になり、日本の巡視船に体当たりをくらわすほどになった。
中国はフィリピンやベトナムとも領海を巡って争っている。1995年には南紗諸島にあるミスチーフ礁に中国が進出し実効支配をした。
今度は南シナ海のスカボロー礁で中国とフィリピンの監視船が睨み合いを続けている。中国では「対話重視」より「実力行使」の声が日に日に大きくなっている。中国機関紙は、「弱小国でも強力な反撃に遭う運命にある」とフィリピンに圧力をかけている。
アキノ大統領は、「わが国の安全と主権が脅かされた時、米国と日本以上に頼りになる友はいない」と、領土紛争問題上の中国の脅威から日米両国が守ってほしいとアピールした。
フィリピン国軍と米軍が実施した第27回合同軍事演習は、過去最大規模の野戦合同演習となった。また、フィリピン政府は南沙諸島周辺海域の陸・海軍力増強に向け、約1億8400万ドルを追加投入した。
中国の外交部は7日、南沙諸島は中国固有の領土であると強硬な態度で主張、フィリピン側の主張を真っ向から否定した。中国は国連に文書を提出、フィリピンが1970年代以降、中国の領土である南沙諸島に侵入を続け、領有権を主張していることを非難し「フィリピンの主張は一切受け入れられない」と強い態度を示した。
中国海軍の各大艦隊は最近、実戦訓練を強化しており、特に南沙諸島を管轄している南シナ海艦隊の駆逐艦分隊は、水上戦闘艦総合攻防訓練を実施した。また、多くの漁業監視船を南シナ海に送り込み、主権を強くアピールしている。中国初の空母「ヴァリャーグ(瓦良格)」号のテスト運航が今年の夏に実施された後、南シナ海艦隊に配属されるという噂もある。
中国とフィリピンとの南沙諸島(スプラトリー諸島)をめぐる領土紛争がエスカレートしており、双方ともに対抗措置をちらつかせ、一発触発の状態に陥っている。
ベトナム政府は中国と領有権を争う南シナ海の南沙(英語名スプラトリー)諸島にある仏教寺院を修復し、僧侶を常駐させる方針を決めた。ベトナムの領有権主張の一環である。初の国産警備艇も就役し、南沙諸島をにらむ南部の海軍基地に配備されており、中国への“反撃”が着々と進んでいる。
230ともいわれる島礁からなる南沙諸島のうち、ベトナムは17島程度の領有権を主張している。この中の複数の島には、ベトナムが1975年まで使用していた寺院が残っている。だが、無人のまま今や朽ち果て、政府は修復と6人の僧侶の派遣を決めた。
直接は、南沙諸島を沖合に望むニャチャンを省都とする、南部カインホア省の人民委員会が主導。6人の僧侶は同省内の別々の寺院に帰属している。それぞれが複数の島に寺院の僧院長として近く、赴く予定で、政府による船の手配を待っているところだという。
今回の決定について、消息筋は「ベトナムの領有権を、中国に認めさせるための努力の一環だ」としている。南沙諸島では1988年、中国、ベトナム両軍が衝突し、複数のベトナム兵が死亡した。僧侶らは、そうした「ベトナム領内で命を奪われた兵士たちの魂も鎮めたい」という。
軍事力に勝る中国は領海を広げていった。中国と周辺国との対立は緊迫が増しており、韓国、台湾、フィリビン、ベトナムはアメリカ軍の助けを望んでいる。もし、アジアにアメリカ軍が駐留していなければ、北朝鮮と韓国、中国と日本の領海問題、中国と台湾問題、フィリピンやベトナムとの領海問題が紛争に発展する可能性が高くなる。
このように中国と周辺諸国とは領土・領海紛争が続いている。北朝鮮や中国に対抗するために韓国、日本、台湾、フィリピン、ベトナムなどの国々はアメリカを頼っている実情がある。
沖縄は、北は北朝鮮から南はフィリピンまでの扇の要の位置にあり、米軍と周辺国との軍事連携には重要な場所である。
アメリカ軍は中国の周辺国との軍事連携で中国、北朝鮮を抑止しようとしている。だから、海兵隊は沖縄から周辺国に出かけて軍事訓練をしている。扇の要に位置する沖縄の米軍基地が周辺国との軍事連携をすることによって中国への抑止力を保っている。アジア情勢をみれば普天間飛行場は必要であることがわかる。
抑止力は海兵隊だけにあるのではなく、アメリカ空軍、海軍、海兵隊と周辺国の連携にある。
米軍基地があるから戦争に巻き込まれない
「米軍基地があるから戦争に巻き込まれる」というのが革新系の政治家や知識人等が米軍基地撤去を主張する根拠である。ところが戦後66年間米軍が駐留し続けているのに沖縄は一度も戦争に巻き込まれていない。戦争に巻き込まれたことが一度もないどころか、沖縄が戦争に巻き込まれそうになったことさえ一度もない。
戦後のアジアの歴史をみると「米軍基地があるから沖縄は戦争に巻き込まれる」ではなく「米軍基地があるから沖縄は戦争に巻き込まれなかった」と考えるのが正しい。
66年間もの長い間一度も沖縄が戦争に巻き込まれたことはなかったのに、「米軍基地があるから沖縄は戦争に巻き込まれる」というのは現実を正しく認識していない。
私は子どもの頃に、「戦争がはじまったら沖縄が真っ先に攻撃される」と言う話を何度も聞いた。嘉手納飛行場と嘉手納弾薬庫の隣で生活していた私はびくびくしたものだ。しかし、沖縄を攻撃するということはアメリカと戦争を始めることである。世界最強の軍事力を誇るアメリカに戦争をしかける国はアジアにはない。アメリカと戦争をする可能性のある国といえば中国が第一候補にあげられるが、中国がアメリカと戦争をしようとしたことは一度もなかった。アメリカが沖縄を統治していた時は、中国漁船が尖閣諸島に侵入することはなく、沖縄の漁師にとって安全な漁場であった。中国漁船が尖閣諸島に侵入するようになったのは沖縄の施政権が日本政府に移ってからである。中国はアメリカ軍を刺激することは避けてきた。アメリカ軍が撤退してから中国はフィリピンと領海争いをしている。
中国が、アメリカ軍が駐留している沖縄を攻撃する可能性は全然なかった。「戦争がはじまったら沖縄が真っ先に攻撃される」といっても、アジアにアメリカと戦争をする国はなかったのだから、「戦争がはじまったら」という仮定は成り立たない。
沖縄にヘリコプター基地は必要
普天間飛行場はヘリコプター基地である。ヘリコプターは空中で停止したり狭い場所にも着陸できるので民間では救急ヘリや山岳の遭難者の救助や小さな離島への物資移動に活躍している。
アジアに駐留しているアメリカ軍が訓練中に事故を起こしたり、台風や地震などで被害が起こった時になくてはならないのがヘリコプターである。アメリカ軍がアジアに大規模に駐留している限りヘリコプター基地はなくてはならない。普天間飛行場には抑止力がないから沖縄に普天間飛行場を設置する必要はないという意見があるが、ヘリコプター基地は抑止力だけが目的ではなく、救助や極地への物資輸送など平常時でも重要な任務を担っている。極地的な紛争や戦争が起こり、アメリカ軍が介入する時はヘリコプターがなくてはならない存在となる。アメリカ軍にとってヘリコプター基地は必要である。
普天間飛行場の辺野古移設は不可能であると発言する米議員でも辺野古移設の代替案として嘉手納飛行場など県内移設を提案しているのであり、県外や国外への移設提案はない。辺野古移設に反対している米議員もヘリコプター基地は沖縄に設置しなければならないという考えなのであって県外移設や国外移設を主張しているのではない。
これまで検討してきたことを根拠にすれば、普天間飛行場は辺野古に移設するしかない。メア氏は辺野古移設ができなければ普天間飛行場は固定化すると発言した。それが現実論である。県内ではメア氏の発言に反発する意見が多いが、ほとんどが感情論である。政治は現実問題であり、感情論や理想論では解決できない。
辺野古移設と嘉手納飛行場以南の米軍基地の撤去、在沖海兵隊8000人のグアム移動は橋本元首相がアメリカ側の抵抗をねじ伏せて実現したことを忘れてはならない。橋本元首相は沖縄の基地負担の軽減には並々ならぬ思いがあった。ところが、嘉手納基地以南の米軍基地撤去には賛成であるが、普天間飛行場の辺野古移設には反対という、現実のアジア情勢を無視した主張のために、16年間も普天間飛行場はこう着状態が続いている。
中国が共産党一党独裁国家であり、尖閣諸島の所有権を主張し、日本の領海を中国の領海であると主張する限り、中国は脅威であり、アメリカと共同で中国の圧力を抑止する必要がある。アメリカ軍がアジアに駐留している間はヘリコプター基地は沖縄に必要である。
普天間飛行場の県外移設・国外移設は不可能であり、地元の辺野古が普天間飛行場の受け入れに賛成しているのだから、辺野古意外に移設できる場所はない。
普天間飛行場移設問題とは関係なく、
一日も早い、
普天間第二小学校の移転を訴える。
Posted by ヒジャイ at 18:22│Comments(0)
│沖縄に内なる民主主義はあるか